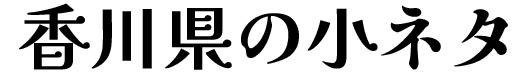萩の花で彩られる寺院
高松市塩江町にある最明寺は、秋になると一面の萩の花に包まれることで知られる寺院です。
香東川上流の小さな溪谷を越え、車で高松市街地からわずか30分。山あいの静かな環境にありながら、見ごろを迎えた萩の花は参拝者を迎え入れてくれます。
門前からすでに咲き乱れる萩の花。
境内へ足を踏み入れると、視界を覆い尽くすほどの萩に囲まれ、本堂さえも隠れてしまうほどの光景が広がります。

萩に包まれる参道
本堂へと続く小道は、両側から萩の枝が伸び、まるで花のトンネルをくぐるよう。
花に抱かれるように進む参道は、この時期ならではの特別な体験です。


本堂とお茶席でのひととき
最明寺の本堂は自由に出入りでき、誰でも気軽に参拝可能です。
また境内では「おはぎ」をいただくことができ、お茶とともに接待してもらえます。
特に庭園の見える席に座れば、色づいた草花と静かな風景に包まれ、日常を忘れるような清らかな時間を過ごせます。


最明寺の歴史
最明寺は鎌倉時代、北条氏の時代に創建されたと伝えられています。
戦国時代には「長曾我部元親に焼かれた」と語られることがありますが、これは史実とは考えにくいものです。
記録に残る焼失は天正13年(1585年)。この年は豊臣軍が四国へ侵攻した時期にあたり、むしろ最明寺は長曾我部方に属していたとみる方が自然です。
当時、長曾我部元親は、山岳修行者たちのネットワークを巧みに利用して勢力を拡大しました。
修験者たちは山から山へと情報や物資を運び、軍事や信仰において重要な役割を担っていたのです。
最明寺も熊野信仰や修験道と深く関わりを持っていたことから、このネットワークの一角にあったと考えられます。
したがって、最明寺を焼いたのは長曾我部ではなく、むしろ長曾我部に与していたために、豊臣軍の侵攻によって焼かれたと解釈するのが自然でしょう。
この件はまたの機会に・・・
熊野信仰と山岳修行の寺
最明寺には那智神社があり、境内には象徴的な二本杉がそびえています。
さらに裏山には那智の滝を模した人工の滝があり、ここが熊野信仰の影響を強く受けた寺であることが分かります。

山深い立地や滝の存在から、最明寺は山岳修行の場でもあったと考えられます。
修行と信仰を通じて四国の勢力と結びつき、歴史の荒波を越えてきた寺なのです。

落ちない岩 ― 受験祈願のスポット
最明寺の裏山には、「落ちない岩」と呼ばれる奇岩があります。
崖の上に今にも落ちそうに見える岩が、不思議と長い年月そのままにとどまっているのです。
この岩はいつしか「落ちない」にちなんで受験祈願の場として信仰を集めるようになりました。
合格を願う受験生や家族が訪れる隠れたパワースポットでもあります。
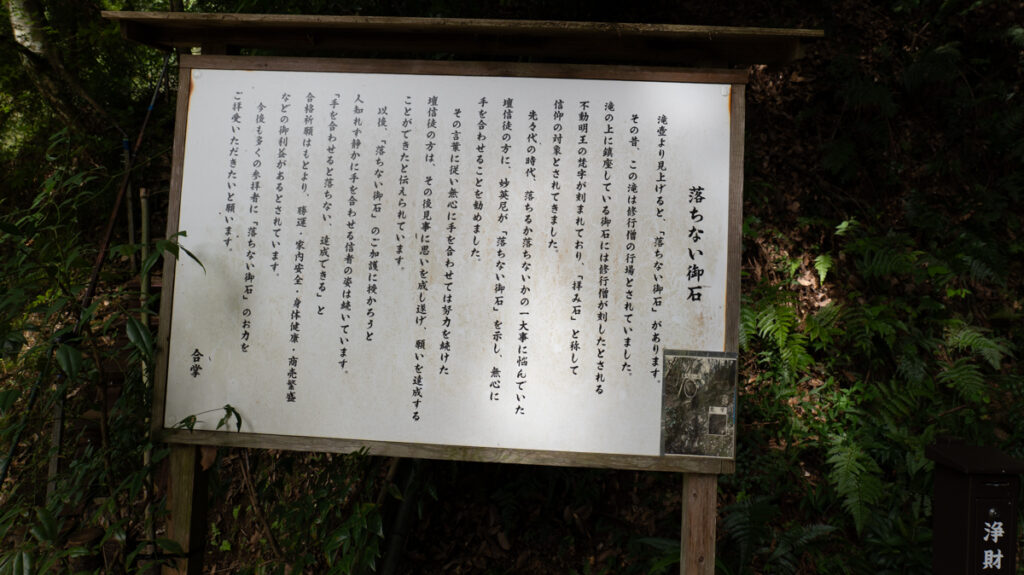

まとめ
高松市塩江町の最明寺は、
- 秋の萩の名所
- 北条氏の時代に創建された古寺
- 長曾我部元親の修験道ネットワークと結びついた歴史
- 熊野信仰と山岳修行の場
- そして「落ちない岩」による合格祈願
と、自然と歴史、そして信仰が折り重なった魅力あふれる場所です。
市街地から30分ほどの距離で、都会の喧騒を忘れて静かな時間を過ごすことができます。
萩の見ごろに訪れれば、花と歴史の両方を体感できることでしょう。