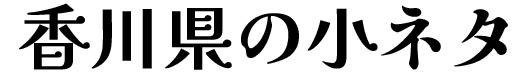高松市庵治町・竜王山とは?

高松市庵治町の竜王山(標高239m)は、庵治半島で一番高い山です。
山頂には「あじ竜王山公園」が整備されており、車で登れる展望スポットとして知られています。
なんとかは高いところが好きという。
私、かもねも高いところが好き。
しかも車で行けるとなれば、はい、ひゃっほーい♬で到着だ。
(歩いて登れとか言うな。文明の力は正義だ)
謎の案内板
そこで見つけた公園の案内板
そこにはこんなことが書かれていました。

「明治28年、八大竜王が祀られ(中略)、前の広場には四本柱が建てられ米の相場・取引が行われていた」
山頂で米の相場!?
なんで山奥で!? 誰も見てないし、これ闇取引か? 裏米マーケット!?
妄想が暴走して止まらない。
でも案内板に書いてあるんだからマジなんだろう。
こうなったら確かめに行くしかない。
いざ山奥へ
展望台(なんか腕時計の文字盤みたいなデザイン)を登って景色を楽しんだあと、さらに山の奥へ。

……きつい。
車でひゃっほーい♬って来たのに、結局山登りしてる自分。
おい好奇心、お前のせいで足がパンパンだぞ。
でも林の向こうに広がる海の景色。うん、この景色は最高だ。

で、その先に原っぱがぽっかり。なんか怪しい雰囲気出てきたぞ。


武神? 八大竜王?
原っぱの前に立っていたのは、兜をかぶった武神が刻まれた石碑でした。
これが八大竜王か?と思ったら……横に「帝釈天」の文字。

ちがーーう!竜王じゃないのかよ!
武士スタイルの神様ってなんなんだ。混乱しかない。
実はこれは明治28年(1895)に建てられた「帝釈天板本尊碑」でした。
案内板と実物、ちょっと食い違ってるじゃないか。
隣の石碑には竜王の名
さらに隣にあった石碑には「竜王」の文字。
しかも裏には「天保二年(1831年)」の刻印がありました。


はい、江戸時代。
つまり竜王が祀られていたのは明治よりも前、江戸のころからだったんです。
ってことは…お米の取引も江戸時代からここでやってたんじゃないの?
証券取引所より先に山頂マーケット開いてたんじゃね?
石碑=広場=取引所?
案内板には「広場に四本柱を立てて取引した」とありましたが、実際には石碑そのものが結界のシンボル。
つまり 石碑の前=広場=取引所 というわけです。
農家や商人たちはここに集まって、竜王と帝釈天に見守られながら
「今年の米はこれくらいでどうだ!」と値段を決めていたのでしょう。
神様の前だからズルもインチキもなし。
信仰と経済が合体した、不思議な山頂マーケットだったわけです。
まとめ
- 高松市庵治町・竜王山公園の山頂には二つの石碑が並んでいる。
- 天保2年(1831年)建立の「竜王碑」
- 明治28年(1895年)建立の「帝釈天板本尊碑」
- 案内板には「八大竜王」とあったけど、実際は帝釈天と竜王。
- この石碑の前で農家や商人が集まり、その年のお米の値段を話し合って決めていた。
- 江戸時代から続いていた可能性が高い。
竜王山公園――ただの絶景スポットかと思いきや、まさかの「山頂お米マーケット跡地」。
歴史を知ると、ただの石碑と広場が一気に怪しい取引所に見えてきます。
今では何の変哲もない山の中のお地蔵さん(いや違うけど)の前の小さな原っぱ。
けれど江戸から明治にかけては、ここが“神聖なお米の取引所”だったわけです。
訪れたときには、この原っぱのあちこちで人々がコメの値段について「あーだこーだ」やってる姿を想像してみてください。
きっとあなたもそのうち、石碑の前で「今日はうどん玉いくらにする?」とか言い出すかもしれません。
庵治竜王山公園
高松市庵治町竜王山
料金 無料
営業
5月~10月 7:00~18:00
11月~4月 8:00~17:00
火曜・年末年始 (火曜祝日の場合、翌平日に休園)