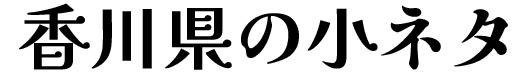讃岐忌部氏って何者?
香川県三豊市豊中町笠田竹田。のどかな田園地帯を抜けると、ひっそりと鎮座する忌部神社があります。
この神社に祀られているのは、建築の神様「手置帆負命(たおきほおいのみこと)」。
名前が長くて一息では読めませんが、日本神話では超重要人物。あの天の岩戸伝説で、岩戸から出た天照大神が入る御殿を建てたという、日本の建築の神様です。
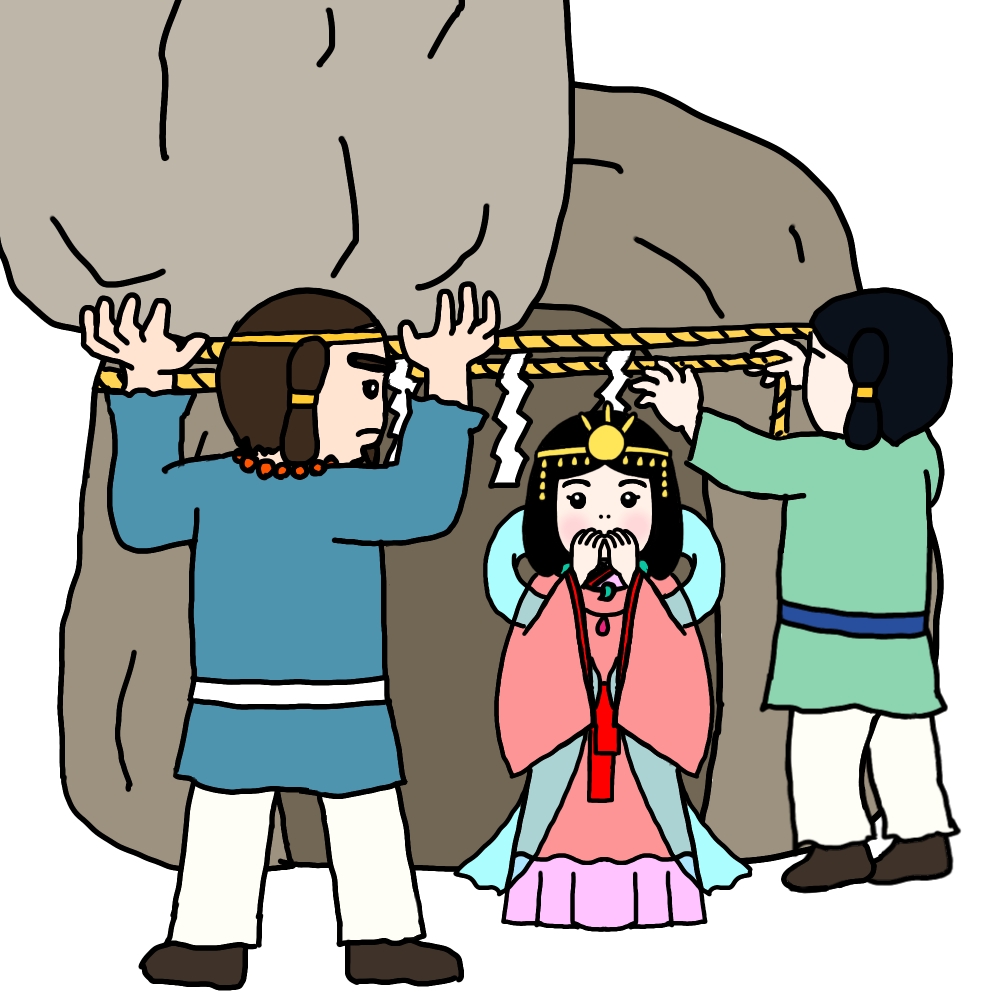
竹を毎年800本も朝廷に献上していた!?
讃岐忌部氏は古代から朝廷に仕えており、なんと毎年800本の竿(竹とされる)を納めていた記録があります。
『延喜式』によれば、臨時祭の「桙木(ほこぎ)」として1200本を納めていたとも書かれており、「讃岐って竹の国だったの?」と思うほどの数字。

この献上は崇徳天皇の時代(1123〜1142年)まで続いたといわれ、朝廷からの「お、今年も来たね」という視線を受けながら竹を送り続けていたわけです。
いまでも全国の棟上げに祈られる神様
驚くべきは、この手置帆負命信仰が現代まで残っていること。
全国で家や社殿を建てる際、棟上げの時に「この神様に祈ってからじゃないと始まらない!」という風習がいまも息づいています。
古代の建築の神様が、21世紀になっても現役で建築依頼を受けているようなもの。
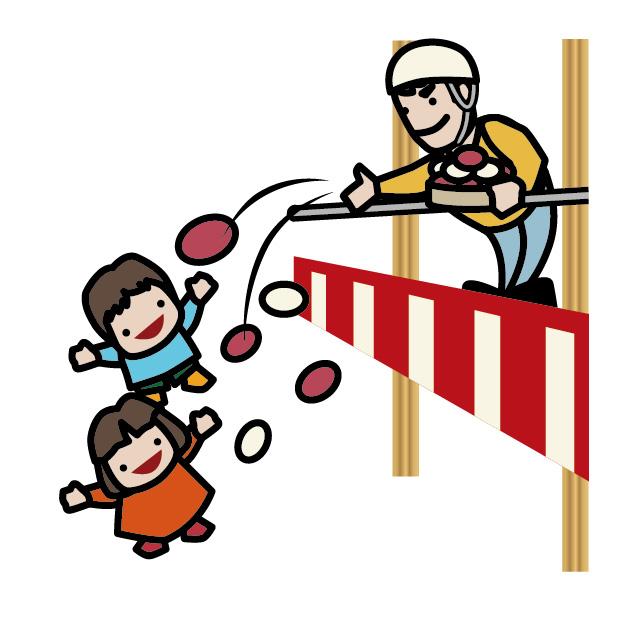
大嘗祭・伊勢神宮との関係
讃岐忌部氏は天皇家の大嘗祭や伊勢神宮の神事でも重要な役割を担っていたといわれます。
阿波忌部は天皇の衣服を準備しましたが、讃岐忌部氏は建物や大幣(お祓いで使う大きな棒)などを整える役割があったと考えられます。
このことは、平安時代の史書『古語拾遺』にも記されており、讃岐忌部氏が国家的儀式に深く関わっていたことがわかります。
古代の国家行事を支えた“影の功労者”だった可能性は非常に高いのです。
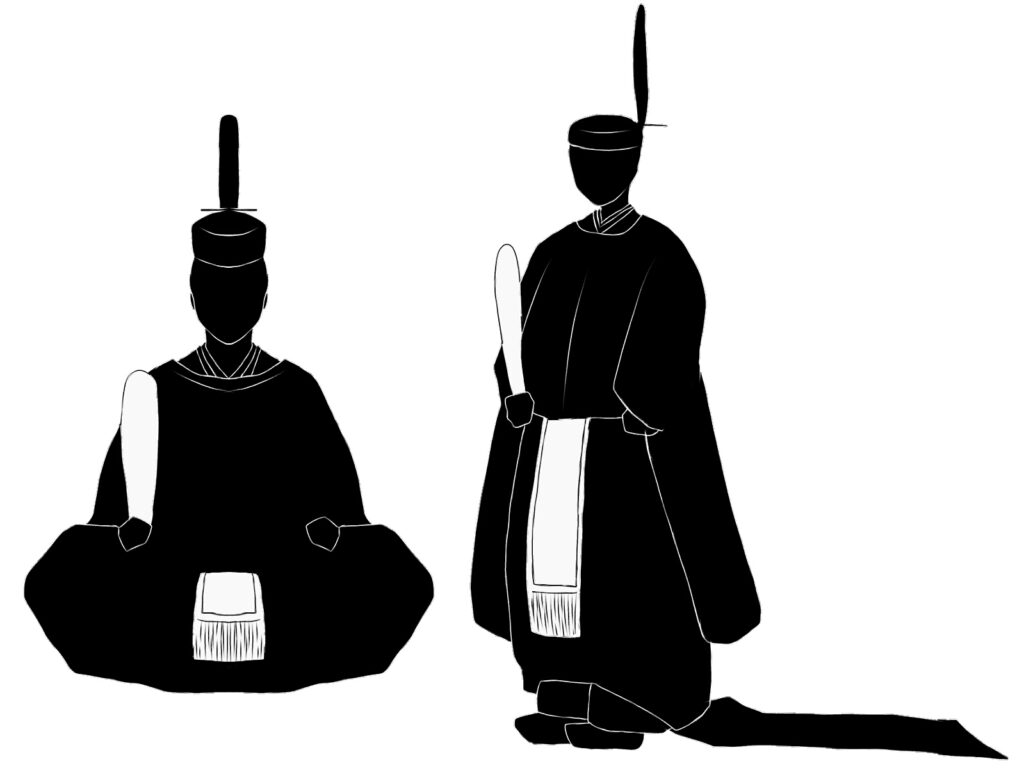
香川西部には忌部氏の足跡があちこちに
香川県西部には、この讃岐忌部氏が住んでいた痕跡が地名に残っています。
「あ、ここ『忌部』っぽい地名だな」という場所は、昔この一族の拠点だったかもしれません。
歴史ファンなら、この地名巡りだけで一日遊べるレベルです。
竹取物語との衝撃の関係
そして最大のサプライズはここから。
日本最古の物語と言われる『竹取物語』。
この中で登場する「竹取の翁」の出自が讃岐国造と記されているんです。
つまり、「竹取の翁=讃岐忌部氏」説が濃厚。
「かぐや姫の実家、香川だった説」…歴史好きにはたまらないロマンです。

まとめ:歴史ロマンあふれる忌部神社
忌部神社は、古代の建築技術と伝承が交差する場所。
香川が誇る建築神の信仰、そして竹取物語との繋がり…。
観光ついでに訪れるのもよし、歴史探訪としてガッツリ巡るのもよし。
行けば「竹」と「建築」の香川ワールドに引き込まれること間違いなしです。
場所
忌部神社. 鎮座地 : 三豊市豊中町笠田竹田214番地